犬マダニ・ノミ駆除剤通販 | ペットくすり
カルドメック、フロントラインプラス、フィラリア予防薬、ノミダニ治療薬等、各種ペット医薬品の格安通販ならペットくすりへ
外部寄生虫
☆外部寄生虫とはどんな病気?
犬の皮膚に寄生する虫といったら、なんといってもノミとダニです。ノミは血を吸うために刺した跡がかゆくなるノミ刺傷だけでなく、その際に体内に入った唾液によって、アレルギー性皮膚炎が引き起こされることがあるのでやっかりです。この虫は、犬同士が接触する際はもちろん。人間のズボンについて家の中に入ってくることもあります。また長い間サナギのままでいることができ、動物が歩く振動を感知すると一瞬で孵化して寄生します。またノミは瓜実条虫、マダニはバベシア原虫など、消火器に寄生する内部寄生虫を媒介する中間宿主でもあるので、それらを防ぐ意味でも、防虫、駆虫することが大切です。
☆外部寄生虫の退治方法は?
スポットタイプと呼ばれる、皮膚に滴下する薬が有効です。犬がなめにくい、薬の後ろにつけます。一度つけると、1~2ヶ月にわたって効果が持続します。ノミに関しては、成虫を駆除するだけでなく、その虫が産卵した卵がサナギにならないようにする成分を加えた予防薬もあります。すでにノミが繁殖していることが明らかな場合には、これを使うとよいでしょう。また、薬によっては、内部寄生虫の回虫や鞭虫、フィラリアの予防薬が含まれているものもあります。この薬をつけている場合、ダニがたくさんいるような、ヤブが多く見られる場所でも、内部寄生虫用の予防薬をつける必要はありません。反対に、あまりノミやダニに気を使う必要がない環境にいる場合は、フィラリアの薬だけを毎月飲ませて、ノミ・ダニの予防薬は数ヶ月おき、回虫などの虫下さしは年1回、という形にすればいいでしょう。また、ヒゼンダ二やニキビダニが繁殖した場合は、薬用シャンプーなどによる治療が必要です。
犬のお薬の御用命は「ペットくすり」まで 商品へのご質問は直接 ショップまでお問い合わせください。 |
犬のアレルギー性皮膚炎
☆犬のアレルギー性皮膚炎とはどんな病気?
「アレルギー」という言葉は一般的に使われていますが、アレルギー性皮膚炎とは具体的にいうと、対外にある、アレルゲンと呼ばれるアレルギーの原因物質に刺激されて起きる皮膚炎。ちなみにアレルゲンの刺激を受けることを医学用語で「感作」と言います。これには、抗原抗体反応という、動物が持っている、カラダを守るためのシステムがかかわっています。
抗原抗体反応は、本来はカラダにとって有害なものを排除しようとする免疫反応なのですが、アレルギーでは、これが必要以上に作用することによって、自分自身のカラダに向けられてしまいます。アレルギー反応においては、好酸球という白血球が、炎症を慢性化させる役割を果たすため、アレルギー性皮膚炎のことを好酸球性皮膚炎と呼ぶ場合もあります。
そして、反応が皮膚にダメージを与えると、皮膚の正常な細胞配列が崩れ、菌や刺激物が侵入を許してしまいやすくなり、また皮脂の分泌も正常ではなくなるため、菌は異常に繁殖してしまいます。こして2次的に皮膚感染症が引き起こされ、症状がより重くなります。そして、この状況は、アレルゲンと接触するごとに、どんどん悪くなっていってしまうのです。
犬のアレルギー性皮膚炎には、アレルゲンの種類によって、大きく分けて食事性、吸飲性、接触性、ノミアレルギー性という四つのタイプがあります。このうち、圧倒的に多いのは吸引性で、全体の60~70%はこのタイプ。一般的にアトピーと呼ばれています。また、食事性のアレルギーは7~15%、接触性のアレルギーは10%ぐらいです。いずれにしても、ありとあらゆるものがアレルゲンとなり得るのです。
人間の花粉症やアトピーでもそうですが、同じような環境に暮らしていても、反応を起こす犬と起こさない犬がいますが、それは、体質の問題です。生まれつきアレルギー反応を起こしやすかったり、皮膚の防御機能が弱かったりする体質があります。また、アレルギー反応とは、反応によって生まれる抗体やサイトカインがたまり、それぞれの犬のキャパシティを超えると現れます。このキャパシティが小さい犬もいます。
アレルギーは遺伝病ではありませんが、アレルギー体質の犬からは、やはり同じ体質の犬が生まれやすいことは確かです。この体質のことを「アトピー素因」と呼びますが、素因を持つ犬に、アレルゲンの原因が加わり、さらに皮膚のケア不足や反対にケアのしすぎ、ストレスといった悪化の要因が加わることで、発症に至ります。
犬のお薬の御用命は「ペットくすり」まで 商品へのご質問は直接 ショップまでお問い合わせください。 |
犬のアレルギー性皮膚炎の主な種類
☆食事性
食べ物の中に含まれるアレルゲンが原因になるもの。アレルゲンになるのは主にタンパク質成分で、肉類、ミルク、卵といったものが代表的。他には穀物などの場合もある。症状としては、かゆみ、皮膚の炎症、フケ。場合によっては消化器にも悪い影響を及ぼすので、吐いたり下痢をしたりといった消化器症状が見られることもある。
☆吸飲性(アトピー性)
ハウスダスト、花粉、カビ、ダニ、塗料、排気ガスといったアレルゲンを吸い込むことで起こるもの。別名アトピー性皮膚炎とも言う。主に顔、四肢、腹部などに炎症を起こし、ひどいかゆみを伴う。炎症部位に細菌が繁殖して二次感染を起こすこともある。遺伝的な要素が関与しているという説もあるが、遺伝子は解明されていない。
☆接触性
生活環境の中のアレルゲンが、皮膚と接触することで発病するもの。人で言えば指輪などに対する金属アレルギーや衣類に対するアレルギーと同じ。その犬に合わないシャンプーや、ノミ取り首輪。また滴下型のノミ駆除剤、カーペット、合成樹脂の食器、樹液などがアレルゲンになる。主な症状は接触部位の炎症、かゆみ、湿疹。
☆ノミアレルギー性
ノミの唾液がアレルゲンとなるもの。通常のノミやダニの刺傷であれば、刺された場所のみがかゆくなるが、アレルギー反応であるため、刺された場所とは関係なく、下半身全域を中心に症状が現れる。閾値にたっするまで時間がかかるため、3歳を超えてから発症するケースが多い。ノミを駆除しても、1ヶ月はかゆみがひかない。
犬のお薬の御用命は「ペットくすり」まで 商品へのご質問は直接 ショップまでお問い合わせください。 |
犬のアレルギー性皮膚炎の主な症状
☆犬のアレルギー性皮膚炎はどんな症状?
症状は、皮膚炎ですから、炎症を起こした部分をかゆがるというのが最初です。接触性の場合は、アレルゲンに触れた場所、つまり首輪なら首のまわり、食器なら口のまわりに炎症が起きます。
その他のタイプの場合は、全身どこに起きても不思議はないのですが、足の裏の他、シッポのつけ根やわき、目のまわりといった場所が多い。また耳の中も皮膚の一部なので外耳炎という形で現れることも多いです。
ただし、アレルギー性皮膚炎は、激しいかゆみがあるのに、初期段階では湿疹などの皮膚症状がいっさい見られないのが大きな特徴。
さらに、二次的に感染症が起こったりする場合もある。発見時期によっては見分けがつかないことが多いのです。できる限り、感染症を引き起こす前の段階で発見して、治療を行いたいもの。そうすれば、症状を軽度に抑えやすくなります。
犬のお薬の御用命は「ペットくすり」まで 商品へのご質問は直接 ショップまでお問い合わせください。 |
犬のアレルギー性皮膚炎の治療法・予防法
☆犬のアレルギー性皮膚炎の治療法や予防法は?
犬のアレルギー性皮膚炎の治療の際は、アレルゲンを突き止めて、そえを防ぐのが一番効果的です。ただし、犬にとってアレルゲンになる物質は一つとは限りません。そのうちのどれが原因なのかを見極めるのは難しく、なかなか排除もできません。
また、検査をしたら、鶏肉、豚肉、牛肉、小麦、米、ハウス・ダスト、ブタクサ、塗料がアレルゲンだとわかったとする。こうした結果が出たとして、これらをいっさい排除した生活を送ることは難しいです。また、アレルゲンだからといってそれをまったく含まない食事にしたら、栄養のバランスが取れなくなるということになりかねませんね。
こういった場合の食事は、特別療法食というのが動物病院にあるので、それを使うといいと思います。アレルゲンをできるだけ除去し、また原因になりづらい成分で作ってあります。全部のアレルゲンは取り除けないにしても、普通のフードよりはいいでしょう。
また、仮に食事性アレルギーでない場合でも、療法食を勧めることも多いです。抗体の量を少しでも減らして、その分闇値のキャパシティに余裕を持たせておきたいためです。アレルギー体質の犬は、食べてすぐ皮膚に症状が出るほどではないにしても、抗原抗体反応は起きているものです。
治療に当たっては、感染症などを併発している場合も多いので、検査の前に対症療法を始めます。抗生剤などの投与の他、シャンプー療法が一般的です。
あまりにひどい時は、抗炎症剤やアレルギーを抑制するステロイド剤を使いますが、あまり長い間使うと副作用の恐れがあるため、症状の緩和に従って、副作用のより少ない薬に切り替えていきます。ただし、基本的にはできるだけ薬の使用は避け、生活環境の改善を行いたいです。最近では、リンパ球に働きかけて、サイトカインの生産を抑制する免疫抑制剤もあります。炎症がひどい場所のサイトカインを減らすために使う、ぬり薬のタクロリムスや、サイトカインの全体量を減らす飲み薬のシクロスポリンといったものが有名です。また、さらに上位の細胞に作用して、抗体の産生を抑制したり、リンパ球のバランスを整えるインターフェロン剤も登場していますが、驚くほど費用がかかってしまいます。
また一部の専門医では、漢方療法や脱感作療法という治療を行う所もあります。脱感作療法というのは、アレルギーの原因を詳しく分析した上で、原因物質のいくつかが入った注射液を定期的に打つやり方。高濃度から始め、だんだん濃度を下げていって、アレルゲンに侵されたカラダを少しずつ反応しづらい体質に変えていきます。こういう方法を試すのもいいですよ。ただし、これらの治療法や注射液に関しては、国内で認可されていないものもあるため、その場合わざわざ海外で薬を作ってもらわなくてはいけません。だから、ある程度のリスクと費用は避けられないのです。
アレルギーは、現段階では完治させる病気ではなくて、管理する病気だと思っていただきたい。だから50~70%症状が改善したらそれで良し、と考えた方がいい。それ以上を求めると、副作用や費用の問題が出てきてしまいますから。病気とともに生きる道を探すように気持ちを切り替えたほうが良いと思います。
まずは生活環境の改善と食事療法。そして適度なブラッシングやシャンプーといった日常のケアを行うことで、炎症がひどくならないように皮膚の状態を保ちたいもの。また、効果がすぐに出ないからといって、病院を転々とするのはやめたほうがいいでしょう。例えばステロイド剤を処方する場合、症状を抑えるためにやや強めのものから始めるのですが、その段階で病院を変わっていると、強い薬の処方が連続して、副作用が重なってしまう危険性があります。
皮膚病は見ていてツライし、「本当によくなるのかな」って不安にもなると思います。獣医師の方に言わせると、3ヵ月は待って欲しいとおっしゃいます。また皮膚病の治療が得意な獣医師なら、「こうなる可能性があります」「こうなった場合は、こうします」という具合に、治療についての詳細な青写真が頭の中に描けるものです。いい獣医師なら、じっくり話を聞いてくれて、病気についての説明をしっかりしてくれるはずです。そんな病院を選び、あせらず気長に病気に向き合っていくことが大切となります。
犬のお薬の御用命は「ペットくすり」まで 商品へのご質問は直接 ショップまでお問い合わせください。 |
犬の外耳炎の原因
☆犬の外耳炎の炎症が起こる原因は?
犬の外耳炎の原因はいろいろありますが、外耳道に蓄積した耳垢に、細菌やカビ、酵母が繁殖して、耳道の粘膜に感染が起こるのが一般的です。また、水遊びの時に耳に水が入り、その水分が耳垢を腐らせることで起こる場合もあります。
その他にも、植物の種や針葉樹の葉、砂など、異物が耳に浸入して、耳道を傷つけたり、刺激することで起きることも。さらに耳疹癖といって、寄生虫、要するにダニが寄生することが原因になっているケースもあります。耳が垂れている犬は、外耳炎にかかりやすく、耳の中の通気が悪くなりやすく、耳道に毛の多い犬はなおさらです。また脂漏体質やアトピー体質の犬にも外耳炎は多いです。
耳の中もアトピーになるのですか?という質問がありますが、耳の中もアトピーになります。耳道も要するに皮膚の一部だからです。アトピー性皮膚炎が、耳から始まるケースもあります。
それに、皮膚の炎症は、さまざまな原因が複合して発症することが多いのです。犬がアレルギー体質だったとして、どこかでアレルギーの原因物質に接触したことがもとで皮膚が弱くなり、ちょうど耳道に耳垢がたまっていて、そこにカビや酵母が繁殖して悪化する、なんてことも考えられるわけです。
原因を突き止めるのは難しく、ましてやアレルギーが疑われる場合は、その原因物質を突き止めなければならいので厄介です。
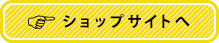 犬のお薬の御用命は「ペットくすり」まで 商品へのご質問は直接 ショップまでお問い合わせください。 |
犬の外耳炎の症状
☆犬の外耳炎の主な症状は?
外耳炎は、耳の穴の皮膚炎ですので、湿疹が出たりして、かゆくなります。ただ、そうなる前に、耳の穴の汚れ方がひどくなってきたら要注意です。黒い耳垢が見られたら、それは耳垢に酵母が繁殖していたり、または耳道が傷ついて、出血していたりする恐れがあります。
かゆみや痛みがひどくなると、頭をしきりに振るようになります。そうなったら、かなり進行している証拠。かゆかったら、その前に直接足で耳をかくしぐさが見られるはずだから、見落とさないようにしてほしいですね。放っておいて、慢性化してしまうと、ひどい場合には耳道が腫れ上がって、耳がふさかってしまうこともあります。また、耳道は顔面神経に隣接しているから、顔面神経まひを起こして、形相が変わることもあります。
また、耳を強く引っかいたりすることで、耳血腫といって耳の軟骨と皮膚の間に内出血を起こすこともあります。そうなると、外耳炎そのものの治療の他に、切開して血を抜いたりといった治療が必要です。耳がキクラゲのように変形して、治った後も元に戻らない可能性があるんです。炎症は、どんどん奥に進行していき、鼓膜より中の中耳に入ると、中耳炎と呼ばれる状態になります。急性のものでは、中耳の中の鼓室と呼ばれるところに、炎症が原因の粘液がたまったり、化膿してうみがたまったりします。さらにひどい場合には、鼓膜の振動を内耳のセンサーに伝える耳小骨という組織が溶けてしまいます。そうなると聴力が失われてしまいます。
中耳炎にまでなると、かゆみを通り越して、耳根部、つまり耳のつけ根が痛くなって、元気や食欲までなくなってきます。そして斜頚といって、首が常に傾いた状態に。さらに炎症が進行して内耳炎にまでなると、一大事。内耳の三半規管の先は、すぐ脳だからです。脳膜炎を併発でもしたら、命にかかわります。さすがに、そんな状態になるまで飼い主が気づかないことはありませんが、外耳炎の症状が見られたら、その段階で必ず病院に連れていって、病気が悪化したり、慢性化しないようにしないといけないです。
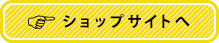 犬のお薬の御用命は「ペットくすり」まで 商品へのご質問は直接 ショップまでお問い合わせください。 |
